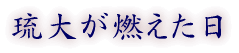
>>TOPページ
![]()
| 10月30日那覇に着いた。喜舎場君らが出迎えてくれた。着いてはじめて気がついたことだが、自分が帰りつく場所はどこかということだった。迂闊にもそのことについては全く念頭になかった。 出かける時は琉大の学寮だった。休暇中であったし荷物はそのままにしておいた。後期が始まっておよそ一月、寮の様子もよくわからない。いきなりそこへ「ただいま」と帰るわけにもいかないだろう。やんばるにひっこむわけにもいくまい。さてどうしようかと困っていると喜舎場君が「うちへ来たらどうだ」という。ひとまずその好意にあまえることにした。お母さんをはじめ家族のみなさんも快よく受け入れてくれた。早めに落付く先を見つけることにして、しばらくやっかいになる。 伊礼君らも集まってきた。およそ40日ぶりである。 この間、大学内外の様子はずいぶんと変っていた。学生会は会長選挙も終え、花城健治君が当選して新しい執行部がスタートしていた。国文科からの中央委員には伊礼君が選ばれていた。 処分問題について学内ではなおゆれていた。会長選挙の中でもその対応が焦点になったようで、処分撤回の基本方針は変っていなかった。大阪できいた情報、「処分学生の救援」に方針を転換したということは、機関決定ではなかったようである。 しかし大学当局の、これ以上問題は広げないという考えは変らず、学生会は新しい執行部はできたものの、当局の許可が得られないため、定期の学生総会も開けない状況にあった。集会禁止令は解かれないままで、新聞、雑誌等の出版も一切止められていた。 例年、大学祭準備の時期にあったが、その開催をめぐってもめていた。処分問題については何らの進展もみられず、総会も開けない状況下で、大学祭どころではないという雰囲気にあった。 そうした中で大学側は、学生会側の総会を開いて対応を決めたという申入れを拒否する一方、大学祭の期日(12月7、8、9日)を指定してきた。これに対し学生会では、中央委員会と各クラブの部長の合同会議を開いて対応を協議、大学側の提案には応じられないということを決めた。 こうして問題はなおひきずっていた。(結局大学祭は、曲折はあったものの開催されたと思う。) わたしの本土行きは、学生代表としての派遣であったので学生会には簡単な報告書を提出した。 学外においては大きな変化があった。10月25日に急死した比嘉主席の後任に、レムニッツァー民政長官は11月1日、当間重剛那覇市長を任命した。 当間市長は、土地問題について一括払い容認の発言をして、県民大会で退陣を要求されたという経緯をもつ。背後では「一括払いを認めてその資金を経済復興にあてるべきだ」と考えていた財界人からの積極的な推薦もあったようである。 この時期、米軍のお眼がねにかなう人物であったのかもしれない。 当間氏の主席就任にともなって、後任の那覇市長選挙が行われることになった。この選挙に、候補者のしぼりこみに失敗した保守系からは仲井間宗一、仲本為美(反当間派)、革新系から瀬長亀次郎の三氏が立候補した。 選挙となると互いの得票合戦で、住民が一つの対米要求でまとまった土地闘争とは様相が異なってくる。いうまでもなく、中心都市の首長選であるからその行方の及ぼす影響は大きい。この年の師走は選挙が中心になって動いた。 12月25日に行われた投票の結果は瀬長亀次郎が当選した。保守系が二派に分れたことも瀬長氏に利したかもしれないが、米軍の執拗な圧力にも屈しない瀬長氏の姿勢を大衆が支持したともいえた。 「オフリミッツ」の解禁に関して「瀬長、兼次は県民代表ではない」という声明を強要してきた米軍にとって、当の瀬長が那覇市長の席につくことは極めて不都合なことで、以後瀬長追放に狂奔することになる。 こうして時が経ち、政治情勢の焦点が変わっていく中で、忘れられたわけではないだろうが、琉大の問題については進展のないまま影が薄れていくような感じがしていた。 除籍のままだから出校するわけにもいかなかったが、学内の情報は伊礼君たちが運んでくれた。いくつかの整理すべきこともあった。 本土へ出かけるとき、学寮の部屋の荷物はそのままにしてあった。その後どうなっているのか、たいしたものはないけれども放っておくわけにはいかない。気は重かったが寮を訪ねてみた。一室6名のかってのわたしの席には新たに学生が配置されていて、わたしの荷物は部屋の隅に積まれていた。舎監の指示によるものだという。顔見知りの学生は恐縮していた。 処分問題はまだケリがついていないのに、ことの処理はさっさとすすめられていることに少しムッとした。その学生に文句をいうわけにもいかず黙っていたが、問題が決着するまでそっとしておくわけにはいかなかったのか。学生側にも抵抗感はなかったのか、内心不満がうずいた。 たいした荷物はないとはいっても、本やノートその他一度には運べない。持てるだけをまとめ、あとは近く取りにくるからと保管を頼み寮を出た。「追い出されたのか」何か空しい気がした。 この間喜舎場君の家に居候していたが、いつまでもそれにあまえているわけにもいかない。落付く場所をさがしていたがなかなか見つからず、探しあぐねていた。そんな時、名嘉順一君が琉大の近くに空き家があるから一緒に借りようかというはなしをもってきた。農学ビルの下の方、カヤ葺きの一軒家で二間に炊事場がある。早速借りることにし暮れに引越した。折しも与那覇君も寮を出されて貸間をさがしていたが見つからず困っていたので迎え入れ、3人で自炊をはじめた。 大学の近くなので、講義の合間や行き帰りに友人たちがよく立寄ってきた。男だけの慣れない自炊だからみんな気をつかってくれて何かを持参してくる。おかげで食料にはこと欠かなかった。学内の様子も伝わってくる。さしたる動きはないようだった。 こうしてこの年は暮れた。 1957年。年が明けた。 前年11月に就任した当間新主席は年頭で「明るい政治、明るい生活環境」を標榜していたが、そのような状況を思わせる年明けではなかった。 久志村の辺野古では新たな土地収用の問題が起こっていた。 1月3日に来沖したレムニッツァー民政長官は、米国の基本方針として地代一括払い、新規収用等、プライス勧告の基本線は動かさないということを表明していた。 これらの問題をめぐって土地総連合では論議がかわされていたが、意見の相違がはっきりと表われていた。かって批判されたことであったが民主党は「四原則は交渉の原則であって条件ではない」ということを党として主張していた。 軍用地主で組織する土地連は「あくまでも従来の四原則を堅持し不退転の意志と信念をもって団結を固める」と、従来の方針を変えなかった。 一方、当間主席は「四原則はそのままは通せない。条件も地域的に千差万別で、一括払いになれば資金の運用を検討したい。」、「四原則貫徹、島ぐるみ運動など、今までの在り方がマイナスとは思わないが、四原則は適当な時期に降ろすべきだ。すでにその時期に来ていると思う。」と語り、はっきりと土地連等の意見と対立していて、運動路線の変更、対米協調(迎合)へと歩みはじめていた。 もう一つの焦点、那覇市長に当選した瀬長氏は、1月5日当選証書が交付され、市長に就任した。瀬長市長の出現にショックを受けていた米軍や保守派は、早速瀬長追い出しの画策をはじめていた。 議会で多数を占めていた保守派(定数30で人民党は3議席)は、直ちに不信任決議の意向を示していたが、就任早々では市民の反撥をかうおそれもある、と行政不能に追いこむ方針に変え、米軍の手をかりて琉球銀行(株の51%は米軍が保有)の融資を止め資金の凍結等、管理職を含めた非協力で市政を麻痺させようと、イジメにかかっていた。(後のこと。市議会は6月17日、24対6で市長不信任案を可決。市長は議会を解散、選挙の結果は市長支持が12議席と倍増、不信任は不能となったが、米軍は布令を改正して瀬長を追放。58年1月12日に行われた市長選では、瀬長氏の後を受けた兼次佐一氏が当選した。) 学内の雰囲気は鎮静化の方向にむかっていた。大学側は当初からの考え方であった「問題の拡大は新たな犠牲者が予測されるからこれは避けたい。処分学生の処遇については責任をもつ」という方針のもと、学生会の動きには敏感に反応する一方、処分学生を本土の大学へ転学させることによって問題の解決をはかろうとしていた。 この方向での説得は各方面で効いていたようである。学生会も進展のない中でいらだたしい気持もあったのであろう、不満をかかえながらもやむを得ないという判断に傾いたようだった。 ようやく1月24日に学生総会が開かれたが、学生処分問題はとり上げない、という条件のもとに許可されたものだった。 しかし、総会が進行し予定の議案が承認されると、「学生処分の撤回要求」の決議案が緊急動議として提出され、そのとり扱いをめぐって会場は一時混乱した。 役員側としては、この総会は中央委員会で決定した事項のみを審議するという条件で大学当局の承認を得ているので、ここで処分問題を審議することはできない。大学側も処分学生の問題については転学なりの具体的な解決策をすすめているといわれるから、この問題をここで取り上げることは処分学生個人にも不利になる、と動議の撤回を求めたが学生側はきき入れず、一時会長は辞意を表明、役員も退場するという場面もあったりした。 結局学生総会としては、大学における学問の自由と自主性を確立するという宣言文のなかに処分問題も織りこむということで結着した。 転学による問題の処理。それは関係団体においても同様な考え方に落付いていた。 教職員会の屋良会長に会ったとき、「処分は不当なことに違いないが、米軍相手のことだから撤回はむつかしいだろう。大学から追放するということは、学業の機会を奪うということである。その学業の機会は県民連帯の中で、いかなる権力といえども奪うことはできないということを示してはどうか。広い意味で勝敗でなく、君たちが本土の大学へいって卒業を全うする。そうすることによって処分の効果をなくすることができる。そのための援助は惜しまない。」と、会長独得の熱っぽい口調で説得された。何となく言いくるめられたような気もしたが、またそういう考え方もあるのかとも思った。 ことは転学についての決断を迫られている。転学ということになれば、処分を認めることにはならないか。(これまでそういう思いが強かった。)処分は不当であるから、あくまでその撤回を要求していくことが正当であろう。だが、(個人的な行動に起因することではないから、関係組織の意向等)四囲の状況は、撤回へむけて居坐ってもそれを支えていけるようなものは感じられなかった。 残念なことに、処分を受けた諸君はそれぞれに散在していて、顔をそろえてこれからの問題(身のふり方等)について意見をかわす機会がもてなかった。大学側では個別に意志確認をとっていた。近くにいた喜舎場、与那覇は「やむを得ないだろう」という意向で、私もそれに同意した。豊川は諸事情から沖縄を離れるわけにはいかない、ということだった。 転学による処理という方向が定まり、大学側ではその手続きに動き出していて、副学長だった仲宗根先生は、学生の受け入れ先を求めて東京、関西を奔走なさっていた。自から処分した学生の救済にまわるという矛盾した極めてやっかいな問題の処理に、先生は心血を注いでいた。沖縄戦でひめゆり部隊を引率して多くの教え子を失ない痛恨の極みであったろう、その心の傷手をかかえ続けていた先生にとって、首をきられた学生を放置するわけにはいかなかったのであろう。後に知り得たことであるが、転学の受け入れ先を求めて雪の京都御所前を通り過ぎたとき、 自からの切りし首をささげつつ 雪の降る中御所を過ぎゆく とその心境を詠まれている。 行く先も決まった。古我知、喜舎場、嶺井は日大、与那覇は同志社大、神田は立命館大へ。島ぐるみの土地闘争、米軍の弾圧、布令の下にある琉大。これら沖縄の情況を投影しながら曲折を経た結着である。東京に滞在していた仲宗根先生から3月10日までに上京するよう連絡が届いた。 いざ沖縄を離れるとなると、これまでのでき事が脳裡をかすめ、いろいろな思いが錯綜して複雑な心境になる。「これでいいのだ」と自からに言いきかせながら、そして、沖縄の心の火種は消えることはあるまい、いつかまた炎となって燃えあがることを信じて、あわただしい準備にとりかかる。 学友や先輩たち、教職員会など数々の支援。その励ましの中、3月6日那覇港から東京へむけ船に乗った。 |