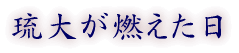開会前のステージでは、琉大学生に帰省学生も加わり、歌声センター(各職場や地域でもサークル活動がふえつつあって、歌ごえセンターもできていた)の仲間も一緒になって、「しあわせの歌」など、にぎやかに歌ごえを響かせ、会場からも唱和の声がきこえていた。 開会前のステージでは、琉大学生に帰省学生も加わり、歌声センター(各職場や地域でもサークル活動がふえつつあって、歌ごえセンターもできていた)の仲間も一緒になって、「しあわせの歌」など、にぎやかに歌ごえを響かせ、会場からも唱和の声がきこえていた。
8時開会、本土折衝から帰った代表団四氏(新里善福、翁長助静、知念朝功、安里積千代)の報告、各団体、政党代表の意見発表が続いた。
各代表は、「アメリカが80万住民の声に耳を傾けないならアメリカに真の文明はない」、「われわれのたたかいは長く続くであろう。他からの支援も必要だが、土地をとられる地元沖縄の団結が何より大切である」、「四原則を守り抜くためには、獅子身中の虫をえぐり出す鋭利なメスも必要だ」、「野蕃なアメリカの政策に対する非協力、対米非服従こそ真の無抵抗の抵抗である。一にも二にも組織の強化につとめよう」と主張した。
学生代表の古我知会長の意見発表の後であったか、那覇消防隊の勤務中の隊員からの「勤務中で大会に参加できないが、ここの高台から皆さんの家屋を守っておりますから四原則貫徹のために心おきなくがんばってください。」と、激励文が届けられ、議長団から披露されると満場指笛と拍手で沸いた。
私は宣言文を読みあげる役目があったのでステージの袖に控えていた。大会の進行は宣言・決議に移り、主席の退陣要求が提案されたとき、いきなり前方の場内から「今の決議に異議あり、反対」の声があがり、場内は一時騒然となった。各弁士の熱弁に、これからのたたかいにむけて一体感に満ちている雰囲気の中での突然のこと、「何ものだ」と人々はいきなり立った。騒ぎの中を出てきたのは那覇高校の仲村渠致彦君だった。彼は那覇高校の文芸部で活動していた。つき合いがあるというほどではなかったが、「琉大文学」を出す中で高校の文芸部とも交流をもっていたので顔は見知っていた。「元気者」という印象があった。
ひと騒ぎある中であったので、彼は意見をのべることはできなかったが、演壇の近くでまわりの人に言い張っているのをきいたところでは、その言わんとしていることは「すべての県民が一体となってといっているのに主席を排除するのはおかしい」ということであったように思う。
大勢集まっている中でのできごと。「群衆心理は何をするか分からない」とその暴走を懸念する見方もある。が、この騒ぎの中でも方言で「タックルセー」と叫ぶ人もいたが、それは怒りの表現で、実際にその発言者が高校生だとわかると間もなく静まった。
大会は締めくくりに近づくとき、20万人と発表された。決議は、比嘉主席、当間那覇市長の退陣要求と学校用地使用制限の布令撤廃要求を決議。また本土との連帯強化のため県民代表を派遣することになり、代表として兼次佐一、瀬長亀次郎を決定、さらに各団体の推せんを経て理事会で決定することになった。
最後に宣言文を読みあげる段になりかなり緊張していた。声もうわずっていたであろうマイクの前で声をはり上げ“宣言”と告げた。
〈宣 言〉
われら80万県民は、今アメリカの自由世界防衛の美名の下に築き上げた原水爆基地拡張のため 新規土地接収と永久土地買上げを強制するプライス勧告によって、その生存を否定されようとしている。
終戦十一年、幾多過酷な犠牲と強制の下に血と涙の悲劇を積み重ねてきたわれわれは、8千万祖国同胞とともに領土の防衛と生存権擁護のため決然として起ち上がった。世界はこの正しいわれわれの抵抗を支持し、あたたかい友情のまなざしを向けて支援と激励の手をさしのべている。
かかる世界の正しい動きに逆い、アメリカ政府とその軍隊は残酷な一方的計画を強行しつつある。今こそ、われわれは断固として屈辱の鎖を断ち切らなくてはならない。われわれは独立と平和と民主主義の旗じるしのもとに、祖国と民族を守り、全県民の土地と生活を守るために四原則を死守する。そして一切のデマゴギーを粉砕し、欺まんを暴露して闘い、長期化と困難を克服し、常にたたかう兄弟たちの先頭に立って「国土を一坪もアメリカに売り渡さない」決意を固め不敗の統一と団結を組んで、鋼鉄のように抵抗する。この決意はわれわれに対するいかなる形の攻撃の前にも絶対不変である。歴史の鉄則の上にたち「正義は必ず勝つ」ことを確信しつつ右宣言する。
大会が終わったのは夜も更けていた。参会者はそれぞれの方向の通路を埋めて帰路につく。大会の昂奮とその余韻を捨て難く、会場を去りかねている学生たちは、プラカードを積み上げて焚きファイヤーストームをはじめ、ひとしきり歌ごえが響いた。会場の無事を見届けて引き上げたが、首里まで歩いて帰ることにした。誘い合ったわけではないが、女子学生を含む十数人で首里への坂道を上る。一つの目標を共にたたかっているという連帯感と充実感というか、快い疲れはむしろお互いを結びつけていく。上り坂、息をきらしながらも時に肩をくみ、歌を歌いながら互いに確かなものを感じていた。
|